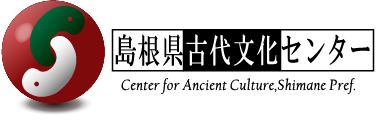第199話 雲南市の赤瓦
榊原 博英 特任研究員
(2026年2月4日投稿)
雲南市三刀屋町の永井隆記念館には、博士が長崎で療養・執筆などを行った如己堂《にょこどう》の複製があり、建物の一部に赤瓦(赤褐色の釉薬瓦で石州瓦とも呼ぶ)が使われています。長崎市に残る如己堂の赤瓦は、三刀屋町多久和にある生い立ちの家の納屋の瓦を運んだことがわかっています。

雲南市では各地で瓦が焼かれた一方、川沿いの輸送で赤瓦が入った可能性もあります。現在でも斐伊川、赤川流域など赤瓦の家を多く見ることができます。今回は郷土誌で概要がわかる、加茂町三代《みしろ》(御代)、三刀屋町里坊《さとぼう》の瓦生産について調べてみました。

赤瓦は石州瓦という名前から、石見で焼いた瓦のイメージがありますが、実際は石見の職人の出稼ぎ、移住に伴い広く生産されています。赤瓦は、特に明治以降に伝統的な黒色のいぶし瓦屋根のなかった海岸部、農村部に普及します。
『三代郷土誌』では三代の瓦生産は、寛政年間から小規模に行われ、天保元年に地元2名、長谷寺住職、石州人2名の5人で本格的に瓦生産が始まりました。赤と黒の釉薬瓦を焼き、赤瓦は来待石粉、黒瓦はマンガン、鉄の釉薬をかけていました。登窯は24室あり、経営者6人で各4窯ずつもち共同で焼いたとされています。
『加茂町誌』には出典が不明確ですが、御代赤瓦組合の登窯は「天保5年登窯12段、安政3年登窯15段、明治10年登窯24段、昭和18年登窯24段、昭和39年登窯15段、昭和53年廃窯」という記述があります。
明治期に段数が増えるのは、近代化の中で製鉄、和紙など伝統的な産業が衰退し、代わるように焼物生産が増えて窯が大型化する石見地域の様相とも似ています。
登窯の部屋数は、石見の登窯と比べてかなり多いようです。石見に残る瓦窯は12室前後、陶器窯で最大23室です。現在残る温泉津やきものの里の登窯でも15段30mの規模で、御代の瓦窯の24段はかなり大型です。窯は斐伊川沿い、長谷寺へ上る山裾あたりで、『加茂町誌』に写真が掲載されています。
『里坊郷土誌』には、里坊瓦の記述があります。大正の初めに出雲市塩冶町から飯国氏が転住し、大正2年に創業、石州から4人の職人を雇っていました。里坊瓦として「○内にサ」の商標で広く販売されました。大戦直前で休止し、戦後の昭和21年に清泉有限会社鍋山製瓦工場として再興し、10年間続いたとあります。
里坊瓦を始めた飯国氏は、塩冶の瓦製造の家に生まれ、その技術の持ち主でした。出雲市塩冶町の赤瓦生産は神門川沿いの半分《はんぶ》で行われました。里坊、三代の瓦生産は神門川、斐伊川を遡るように、出雲市側から石州の赤瓦の技術が伝わったと考えられます。


なお、里坊瓦の製作道具は、雲南市教育委員会所蔵の民具の中に確認できました。商標の「○内にサ」を彫った軒桟瓦の木型、成形台、叩き板などが残っており、往時を知ることができる貴重な資料です。また、出雲市塩冶町の半分瓦窯跡は斐伊川放水路建設に伴い発掘調査が行われました。赤瓦や、瓦を焼く際に間に挟む窯道具などが出土し、里坊瓦と同笵型ではありませんが、中心紋様、脇唐草の配置が似た瓦もあります。残された道具や出土瓦は、半分と里坊の赤瓦生産の技術、人のつながりを示唆する資料かもしれません。